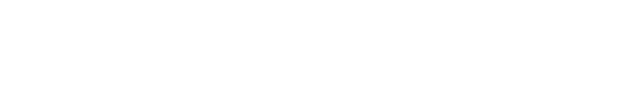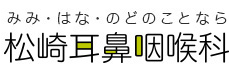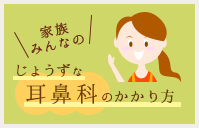みみの症状と病気
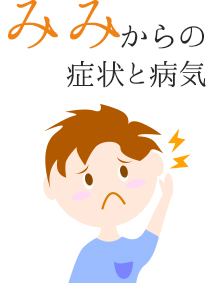
中耳炎耳が痛い/発熱/耳だれがでる/耳の詰まった感じがする/聞こえが悪い
中耳炎は中耳という鼓膜の奥にある鼓室という空洞になっている周囲が炎症を起こした状態です。
急性中耳炎
細菌が中耳に感染して起こる急性の炎症です。風邪をひいたあとなどに、のどや鼻にいるウイルスや細菌が耳管を通って中耳に感染して起こり、耳が痛み、聞こえが悪くなったり、耳だれがでることもあります。副鼻腔炎からなることもあります。小さな子どもでは耳痛を訴えず発熱のみのこともありますので、耳を気にしている様子がみられる時は早目に診察を受けましょう。
滲出性中耳炎
中耳の内部に水(滲出液)がたまり、軽~中等度の難聴が生じます。急性と異なり、痛みや熱を伴わないこともあり、自覚できずに発見が遅れることがしばしばあります。小児の難聴の原因では一番多く、急性中耳炎の治療が不十分だった場合などに移行しやすくなります。 テレビの音が大きかったり、呼んでもふりむかない、耳がふさがった感じがする、といった場合には滲出性中耳炎の可能性を疑った方がよいでしょう。放置すると難聴が続いたり、合併症に繋がることもあります。
真珠腫性中耳炎
鼓膜の一部が内側に入り込んで袋状になり、真珠腫(真珠状の白い塊)ができます。多くは滲出性中耳炎などを繰り返したり、鼻すすりを長期間したりした結果、くぼみができ、そのくぼみに耳垢などがたまって真珠腫ができる病気です。健康な状態では自然に排出される耳垢ですが、くぼみに溜まることで細菌や真菌が増殖し発症、進行すると炎症を伴って内耳や周囲の骨や神経を破壊していきます。耳だれ、難聴、めまい、耳鳴りや顔面神経麻痺などを合併することもあります。治療は入院して手術が必要になることが多いです。
慢性中耳炎
急性中耳炎が悪化すると鼓膜に穴があき、中にある膿を出して炎症を治そうとします。あいた穴は自然に閉じますが、中耳炎を繰り返したり、治り方が不十分だとこの穴が閉じなくなることがあります。それにより外耳道を通して中耳に水が入ったり、風邪などにより細菌が入ることで耳だれを繰り返すなどの症状がでます。鼓膜に穴があいて音が伝わりにくくなるため難聴になります。また、内耳にも影響を及ぼすと、めまいが起こることもあります。
外耳炎(外耳道炎)耳が痛い/発熱/耳だれがでる/かゆい
皆さんが耳掃除をされる、耳の入口から鼓膜までの「耳の穴」に当たる部分を外耳道といい、その部分に炎症が起きる症状が外耳炎(外耳道炎)です。外耳炎は耳掃除などでできた小さな傷に不衛生な手で耳を触り、そこから細菌が感染・増殖して皮膚に炎症を起こすようになります。痒みや痛み、灼熱感や耳閉感、耳鳴り、難聴を訴えることもありますが、ほとんどの場合、炎症がおさまればこれらの症状も消えます。しかし酷くなると耳だれといって耳から膿のような液体が流れ出るようになることもあります。外耳道が健康で炎症が軽度であれば、通常は放置しても自然に直りますが、症状が1〜2日経過しても改善しない場合は、耳鼻科を受診したほうがよいでしょう。繰り返される外耳道炎は、糖尿病や免疫疾患など全身状態の悪い人にみられることがあるので注意の必要があります。
突発性難聴耳が詰まった感じがする/聞こえが悪くなった/耳鳴り
耳の病気を経験したことのない人が、明らかな原因もなくあるとき突然に音が聞こえにくくなる病気が突発性難聴です。原因は完全には解明されていませんが、聴こえの神経への血流障害やウイルス感染による障害が指摘されています。睡眠不足や風邪が何らかの原因の引き金になると考えられているようです。症状としては軽いものから重いものまで様々ですが、突然に聴こえが悪くなったり、場合によっては耳がふさがった様な感じになって発症します。また、耳鳴りやめまい、吐き気が伴うことがあり、耳が詰まった感じがする軽症の難聴もあれば、片耳がまったく聞こえない重症の難聴もあります。通常、片耳に発生することが多いのですが、まれに両耳に同時に発生することもあります。重症であればもちろん病院を受診すると思いますが、もし軽症の場合でも聴神経腫瘍という難聴だった場合は症状が脳にまで及ぶこともあり、また早期であれば治る病気でもあるため、突発性難聴が疑われる場合、耳鼻咽喉科を受診することで早期に診断を行い、できるだけ早く治療を開始することが重要です。
顔面神経麻痺目が閉じにくい/口から飲みものがこぼれる
顔面神経麻痺は、顔面神経によって支配されている顔面筋の運動麻痺です。急性あるいは亜急性に発症します。原因疾患が明らかな症候性顔面麻痺と、原因不明な特発性顔面神経麻痺(ベル麻痺)とに分けられます。 原因疾患として多いのは、ヘルペスウイルス感染症で、典型的には口唇(こうしん)ヘルペスを以前患った方が突然の顔面神経麻痺で発症します。ほかには腫瘍や代謝疾患が原因となる場合もあります。顔面神経は側頭骨の中を走行しているため、中耳や内耳の病気が原因となって顔のしびれ、ゆがみ等の顔面神経麻痺様の症状が出てくることがしばしば認められます。神経が絡んでくると治療の難易度が難しくなりがちです。顔面神経の病気の診断、治療は耳鼻咽喉科医が専門とする領域でもありますので、少しでも症状が軽いうちに早期受診をこころがけましょう。
メニエール病めまい/耳鳴り/聞こえづらい/吐き気
メニエール病は内耳の病気で、繰り返すめまいに難聴や耳鳴りを伴うものです。耳鳴り、低音難聴、耳の中がこもったような感じから、めまいの症状を起こすようになります。めまいが激しい時は、これらの症状以外にも吐き気、冷や汗、動悸などが起こり、これらのほうが苦しいこともあります。めまいや耳鳴りなどの症状が断続的に出る「活動期」と一時的に症状がなくなる「間歇期」を繰り返し、間隔は数日、数週間、数カ月、あるいは1年に1回など人によって違います。一般的には、片側の内耳の障害ですが、まれに両側とも症状がでることもあります。原因は不明ですが、その病気の本体は内耳の水ぶくれ状態(内リンパ水腫)ということがわかっています。そのため、ストレスをためない生活や内リンパ水腫を悪化させる「過剰な水分摂取」そして「喫煙・飲酒」「カフェインの過剰摂取」も控えるとよいでしょう。
良性発作性頭位性めまい症めまい/吐き気
めまいとは、直立の姿勢を保とうとしてもそれが困難な状態や、静止しているはずのものが動いているように見える状態を指します。直立の姿勢を保つことができるのは、平衡を保持する機能が備わっているからですが、それらが機能しなくなったときにめまいが生じます。良性発作性頭位性めまい症では、回転感、不動感、上下前後などへ動くように感じるめまいの症状が起こります。頭を動かしたとき、頭をある一定の方向へ動かしたとき、あおむけから寝返りを打つとき、座った姿勢から横になったとき、めまいがする。まためまいは数秒から十数秒で治まる、バランス感覚が少し悪くなった、乗り物に酔いやすくなったなどが自覚症状としてある場合は、良性発作性頭位性めまい症の可能性があります。めまいの原因の中で内耳に関連するものは最も多いため、めまいになった方はまず耳鼻咽喉科に受診してみてください。神経耳科という分野では、めまいを主として扱っており、脳疾患や循環器疾患を含めためまいを起こす病気の原因や程度を総合的に診断します。